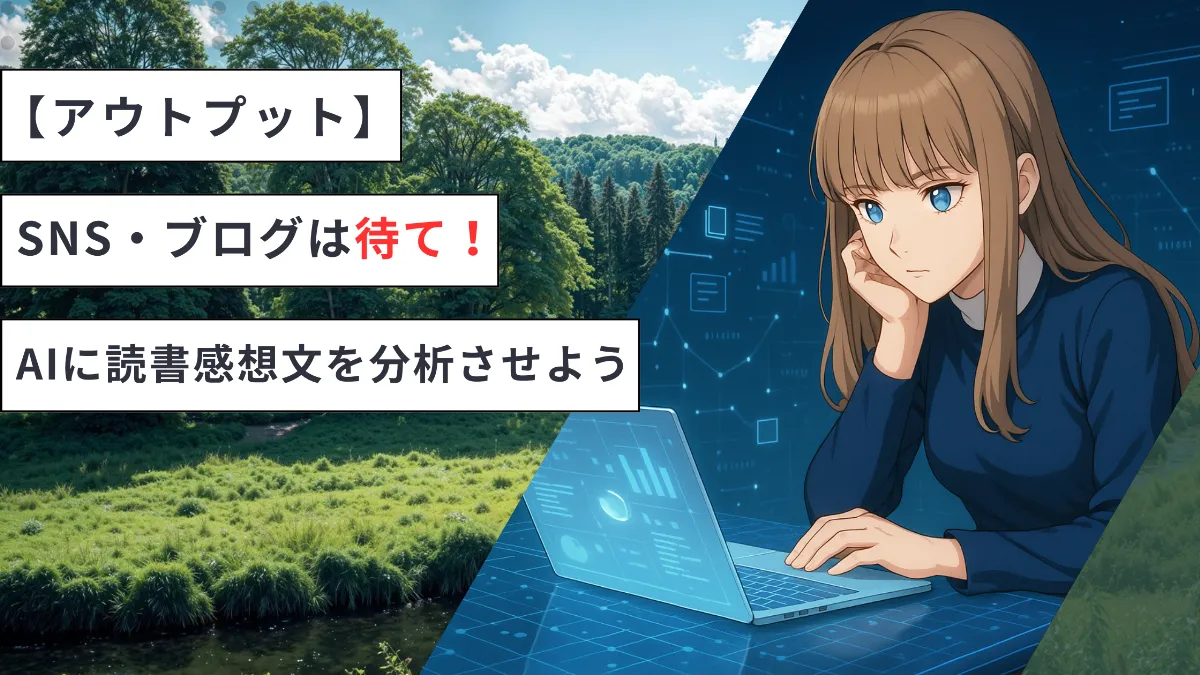- 本を読んだけど、感想文の量が少ない
- 感想文を誰かに評価してもらいたい
- 感想を書いて自分の考えを整理したい
「感想をブログにとにかく書け」という主張があります。
アウトプットは大事だけど、ブログ・SNSに書くのは早すぎます。
なぜなら、実は感想文の本当の価値は、もっと個人的なところにあります。「自分の考えを整理し、深めるためです」ということです。
このブログ記事では、読書感想文が苦手なあなたにこそ知ってほしい、AIを味方につけて自分の考えを深める方法をお伝えします。
大切なのは、最初から完璧な文章を書こうとしないことです。まずは自分の本音を言葉にすることから始めましょう。
感想は誰にも見せない前提で書く
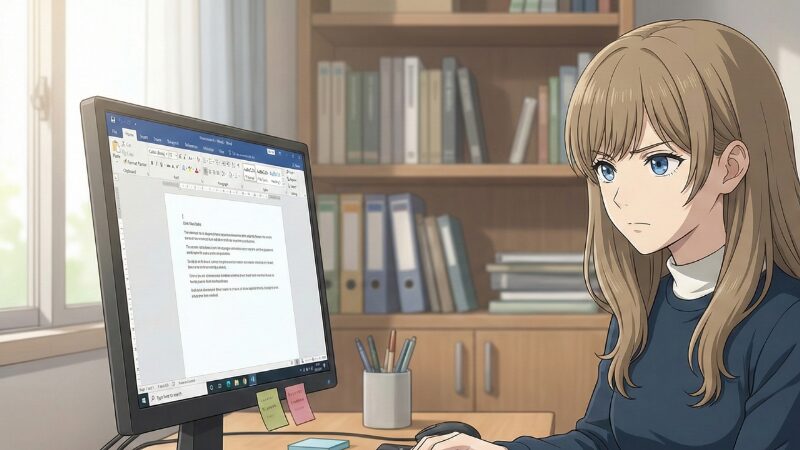
多くの人は感想文を書き始めるとき、「SNSやブログに投稿すること」を真っ先に思い浮かべます。
しかし、感想文を書くうえでSNSに感想を書くことはやめた方がいいです。
なぜなら、人に見せる前提で書くと、無意識に 「他人の目を気にした文章」 になってしまうからです。
- つまらないと思われたくない
- 無難にまとめたほうが安心
- みんなと違う意見を書くのは怖い
自分の思考を整理するための文章では自分のために書いてみましょう。
まずは 「誰にも見せない前提で書く」 ことから始めましょう。
人に見せることを考えない状態で書けば、本音で文章を書くことへの抵抗もなくなります。
このステップを飛ばしていきなりネットに投稿しようとすると、本音が書くことができません。
まず「自分と向き合うための練習」だと考えて、自由に書き出すところから始めてみてください。
読書を始めた人でもできる感想の書き方

感想を書いたら、やっぱり評価してもらいたいものです。書くだけだとつまらないものですから。
この項目では、感想を書いて、AIに評価してもらう方法についてステップ順に解説します。
- 【ステップ1】ワードやメモ帳に感想を書いてみる
- 【ステップ2】下手くそな感想でもいいから書いてみる
- 【ステップ3】書いた感想をAIに分析してもらう
【読書を始めた人でもできる感想の書き方・ステップ1】ワードやメモ帳に感想を書いてみる

「誰にも見せない前提で書く」が大切だとしても、「では何に書けばいいの?」と迷う人は多いでしょう。
紙のノートに書く方法もありますが、私は断然デジタルツールをおすすめします。理由はシンプルで、紙はなくすからです。
書いた感想が紛失したり、読み返したいときに見つからなかったりと管理が大変です。
一方、パソコンやスマホなら、ファイルとして保存しておけば半永久的に残せます。
「○○ 読書感想文」のようにファイル名をつけておけば、検索で一発で見つかります。
私は以前はMicrosoft Wordで感想を書いていました。
最近はマインドマップや電子書籍への直接メモを多用しています。
特に電子書籍に書き込む方法は読んだページと感想が紐づくため、あとから見返すときに非常に便利です。
電子書籍のメモはPDFにして保存すれば、整理もしやすくなります。
最終的にはAIに読み込ませて分析させるので、どのツールを使っても構いません。あなたが一番使いやすいものを選んでください。
もっとも重要なのは、完璧なツール選びではなく、「とりあえず書き始める」ことです。
まずは気負わず、自分が一番すぐに使えるツールでアウトプットを始めてみましょう。
【読書を始めた人でもできる感想の書き方・ステップ2】下手くそな感想でもいいから書いてみる
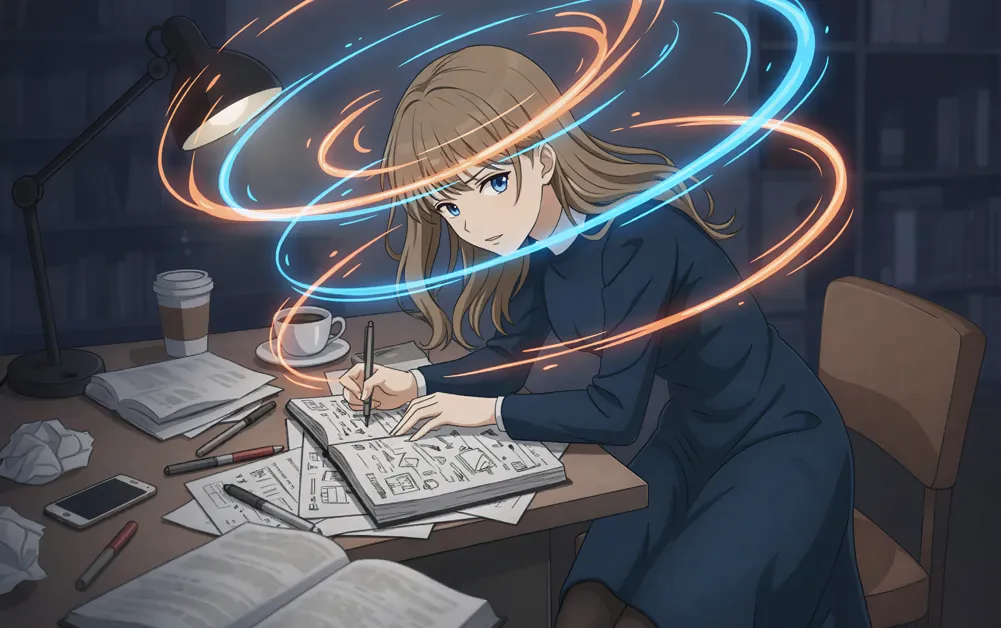
「何をどう書けばいいのか、やっぱりわからない」
そう感じる人は非常に多いです。
しかし、まず大切なのは 「下手でいいから書いてみる」という心構えです。
感想文は誰かに評価されるための文章ではありません。
最初は「ストレス発散」だと思って、心の中のモヤモヤを書き出すだけで十分です。
私も最初からうまく書けたわけではありません。実際の例を紹介します。
「おうちストレス」を読んだ感想について
3分間運動することは体にいいからやりましょうと言う意見に賛成です。何故なら、3分間なら運動習慣のない私でもできそうだからです。
運動しないでゴロゴロしているだけでは駄目だとわかった。
何もしないで1日を過ごすのは大変だ。
この程度で十分です。
改行や文末表現を整える必要もありませんし、文法を完璧にしようとすると筆が止まってしまいます。
慣れてきたら「なぜそう思ったのか?」と自分に問いかけ、根拠を付けてみましょう。
文章が書くきっかけがつかめない場合は、以下のテンプレートを参考にしてみてください。
「〇〇」を読んだ感想について
- 【印象に残ったこと】:読み終えて一番心に残ったことや、感情が動いた部分を自由に書く。
- 【賛成意見】:筆者の意見や、作中の出来事で自分が共感したこと、納得したことを書く。
- 【反対意見】:共感できなかった点や、おかしいと思ったことに書く
無理にテンプレートに従う必要はありません。
しかし「何を書けばいいかわからない…」という状態になったら、テンプレを利用してください。
【読書を始めた人でもできる感想の書き方・ステップ3】書いた感想をAIに分析してもらう
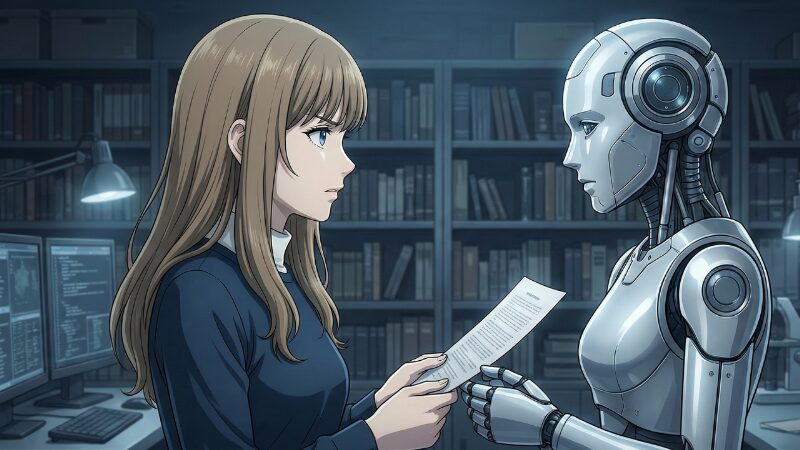
感想文が書けたら、次のステップは AIに分析してもらうことです。
AIは文章を自動生成するだけでなく、「あなたの思考を整理し、気づきを増やしてくれるパートナー」として活用できます。
先ほどの「おうちストレス」の感想文を例に、AIに分析してもらいましょう。
Geminiに以下のように指示を出します。
「おうちストレス」を読んだ感想について
3分間運動することは体にいいからやりましょうと言う意見に賛成です。何故なら、3分間なら運動習慣のない私でもできそうだからです。
運動しないでゴロゴロしているだけでは駄目だとわかった。
何もしないで1日を過ごすのは大変だ。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
この感想を分析・アドバイスして
AIに分析を頼むときは、まずはシンプルに『この感想を分析・アドバイスして』でOKです。
この短い文章の中に、心理的な変化がしっかりと表れています。
ハードルの設定が適切: 「運動習慣がない」という現状を認めつつ、3分という「具体的な数字」に反応できています。これは、脳が変化を拒絶しない絶妙なラインを突いています。
「何もしないことの辛さ」への気づき: 「ゴロゴロしているのは楽なようで、実は精神的にしんどい(1日を過ごすのが大変)」という事事実に気づけたのは大きな収穫です。これは専門用語で**「活動不足による抑うつ感」**を理解し始めた状態と言えます。
素直な自己評価: 「ダメだとわかった」という反省が含まれており、改善への意欲(動機付け)が生まれています。
2. さらに良くするためのアドバイス
もしこの感想をブログに書いたり、誰かに伝えたり、あるいは自分のノートに深掘りして記録したりする場合は、以下のポイントを意識するとより深みが増します。① 「なぜ」3分ならできると思ったのかを具体化する
「3分」という時間を、日常生活の何に置き換えられるか考えてみましょう。(例)「カップラーメンを待つ時間と同じだと思えば、自分にもできそうだと感じた」
② 「ゴロゴロ」の体感を言語化する
「何もしない1日が大変」という部分をもう少し詳しく書くと、説得力が増します。(例)「ずっと寝転んでいると、体だけでなく心まで重くなっていくような感覚があった。本を読んで、その『重さ』の正体が活動不足だと腑に落ちた」
③ 「最初の3分」に何をやるか決める(宣言する)
感想の最後に、具体的なアクションプランを付け加えると、読書が「知識」から「体験」に変わります。(例)「まずは明日から、テレビのCM中にスクワットをすることから始めてみたい」

AIはいっぱい文章を書いてくれるので、考えるネタがありますね。
AIはあなたの書いた文章を客観的に分析し、テーマごとに分類してくれます。
最初はアドバイスを見て、「なんか違うぞ」と思うことをワードに書き足せばいいです。
たとえば、AIが示した以下のような説明を読んで…
「ずっと寝転んでいると、体だけでなく心まで重くなっていくような感覚があった。本を読んで、その『重さ』の正体が活動不足だと腑に落ちた」
「なんか難しい表現だけど、何を言ってるんだ?」と違和感を覚えることもあります。
AIの文章を読んだ違和感こそが「あなたの考えを深めるヒント」です。
実際、私はこう感じて書き加えました。
私の場合、「ゴロゴロしていると昼寝してしまい、逆に気分が悪くなる」と思った。
AIと自分の意見のズレを比較すると、自分の本音が整理され、より深い理解につながります。
AIにすべてを任せるのではなく、「AIと一緒に考える」というスタンスで臨むことが大切です。

AIは本当に色んな分析をしてくれるので考える材料を作ってくれます。
重要なのは、AIに丸投げすることではなく「AIと一緒に考える」です。
AIは多角的な視点を与えてくれるので、
- 新しい解釈が生まれる
- 自分では思いつかなかった深掘りができる
とても便利な思考補助ツールになります。
感想文は、自己理解を深めるための大事なステップです。
AIをうまく活用して、あなたの「考える力」を無理なく鍛えていきましょう。
最後:AIに感想を見てもらおう
感想を書くことは自分に向けて書くことが大事です。感想文の評価はAIがしてくれます。
AIが評価を見て、自分で考えるきっかけを増やしていけばいいのです。
- 誰にも見せない前提で本音を書く。
- AIをパートナーにして、自分の考えを深める。
- メモ・ワードならファイル名からファイルを探せる