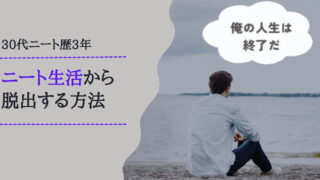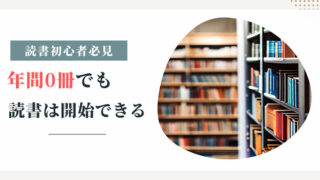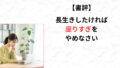- 簡単な本を読めというけど、プライドが邪魔して読めない
- いいから読める本を教えてくれ
- 簡単な本を選んでばかりいると、頭が悪くなる
読書を始めようとしても、どんな本を選べばいいのかわからずに悩んだ経験はありませんか?特に読書に苦手意識を持っている人ほど、「難しい本を読まなければならない」と思い込んでしまいがちです。
私自身も最初は難しい本を読もうと思って、なかなか読書ができませんでした。
結論は簡単な本からスタートするのが効果的です。
- 難しい本を読まないと駄目だと思い込んでいる人
- 紙の本以外を読んでいない人
- 読書をしていない人
簡単な本を避けていた過去の経験
私はかつて、「小学生向けの本なんて読む意味がない」と思い込んでいました。「大学を卒業した自分が、そんな本を読むのは恥ずかしい」と意地を張っていたのです。
それどころか、難しい本を読んで感想をSNSに投稿すれば、「すごい!」と周囲に評価されるのではないかと期待していました。
しかし、現実は違いました。難しい本を開いても内容が理解できず、結局途中で挫折することがほとんどだったのです。
さらに、「簡単な本を読んでいるところを家族に見られたら、バカにされるかもしれない」という不安もありました。こうした理由から、私は簡単な本を避け続けていました。
他にも以下のような理由がありました。
- 難しい本を読めば、すぐに知識が身につくと思っていた。
- 「小学生向けの本は、自分には必要ない」と考えていた。
- 簡単な本を読むことが、これまでの自分を否定するように感じた。
- 図書館に簡単な本があることを知らなかった。
こうした思い込みが積み重なり、私は「簡単な本を読むこと=恥ずかしいこと」と決めつけていたのです。
簡単な本を選ぶようになった理由
私は30歳を前にして、「このままではまずい」と強く思いました。理由は以下の通りです。
- 文章だけの本が読めない
- 面接対策の本が読めない
- 就活をサボるために図書館で時間つぶしをしていた
「このままでは、文章だけの本を読めないまま30歳になってしまう」。
そう思った私は、「とにかく簡単な本から始めよう」と決意しました。
図書館で行き、小学生向けの歴史の本や、イラストが多めの解説書を手に取りました。
少しずつ内容が理解できるようになり、「本を読むこと=難しい」という思い込みがなくなっていったのです。
難しい本を無理に読もうとするよりも、今の自分に合った本を選ぶことが大切なのだと気づいた瞬間でした。
簡単な本の選び方
本をまるで読めなかった私でも、適切な本を選ぶことで、読書を楽しみながら知識を身につけることができます。
簡単な本を選んでしまえば、後は流れで上手くいきます。
では、どのように簡単な本を選べばよいのでしょうか?
マンガや図解本からスタート
まずは「マンガでわかる〇〇」や「図解で学ぶ〇〇」など、ビジュアルが豊富な本を選びましょう。
文字だけの本よりもとっつきやすく、視覚的に理解しやすいのが特徴です。
例えば、歴史を学びたい場合は、マンガで描かれた歴史書を選ぶと、人物や出来事の流れがイメージしやすくなります。
初心者向けの本には、図解やイラストが多く、専門用語も少ないため、内容を理解しやすいという利点があります。
簡単な本から始めることで、基礎知識や全体の流れを無理なくつかむことができます。
映像を活用
本を読むのが苦手なら、まずは映像を活用するのも有効です。
人類の歴史に興味があるならNHKスペシャルを見ることで、大まかな流れをつかむことができます。
その後関連する本を読むことで、より深い知識を得られます。

映像なら導入に最適!

最初はハードルを下げよう。
また、ウマ娘が好きなら、その興味を活かして学びを深めることもできます。「ウマ娘をきっかけに競走馬に興味を持った」という人は多いでしょう。
例えば、ライスシャワーのG1レースの映像を見た後に、ライスシャワーに関する本を読む・・・。
その流れなら理解が深まります。
映像で馬の走りやレースの雰囲気を感じた後に文章を読むと、よりリアルに想像しながら内容を理解できるのです。

買うなら、公式のレースを見て、図書館で本を借りた後よ。

お金を払ってダメだった時の喪失感を避けよう。
読む本のレベルを段階的に上げる
最初から文章ばかりの本を読むのではなく、段階的にレベルアップしていくのが効果的です。
- DVD・動画(NHKスペシャル・スポーツ)
- マンガ形式の本(マンガでわかるシリーズ)
- 図解・図説の本(写真や図が多く、専門的な内容がわかりやすく説明されている本)
- 文章だけの本(小説や専門書など、文字が中心の本)
このようなステップを踏むことで、無理なく読書の習慣をつけることができます。
読み返すことの重要性
読めない本に挑戦したとき、途中で挫折することもがあります。そんなときは、1度読んだことのある本をもう一度読んでみるのも良い方法です。
同じ本を繰り返し読むことで、以前は理解できなかった部分が分かるようになり、知識が定着しやすくなります。
また、複数の本を併読することも効果的です。例えば、同じテーマについて異なる本を読むことで、理解が深まることがあります。
もし1冊の本で分からない部分があったら、別の本で同じテーマについて調べると、新しい視点から学ぶことができるのです。
簡単な本を図書館で借りてよかったこと:
簡単な本から読書を始めたことで、さまざまな変化がありました。
金銭的な負担がゼロに
図書館を利用することで、本を買わずに済みました。
最初は「どの本を選べばいいのかわからない」と思っていましたが、無料で借りられるので、気軽にいろいろな本を試せるようになったのです。
最初に選んだのは「マンガでわかる歴史」のような入門書でした。もし内容が難しくても、違う本を試せばよいと考えられるため、読書へのプレッシャーが減りました。
本の選び方が楽になった
どんな分野の本でも、まずは「マンガ・DVD・初心者向けの本」から入ればよいとわかり、本選びに迷わなくなりました。
日本史を学びたいと思ったとき、最初にマンガ版の歴史書を読んで、その後に図解の本、最後に文章だけの本へとステップアップしました。
この流れを意識することで、知識がスムーズに身につき、読書への苦手意識も減っていきました。
また、図書館で借りた本なら、「思っていたのと違ったな」と感じたときに、無理に最後まで読む必要がありません。
気軽に別の本を試せるので、結果的に自分に合った本を見つける練習にもなりました。
特に、「1度買ったら最後まで読まないともったいない」と感じていた私にとって、この方法は読書を続けるうえで大きな助けになりました。
スキマ時間に読めるようになった
以前は「本を読むのは時間がかかるし、疲れる」と思い込んでいました。
しかし、簡単な本から始めたことで、少しの時間でも読書ができることに気づきました。例えば、朝の通学時間や寝る前の10分など、ちょっとしたスキマ時間を使って読む習慣がついたのです。
さらに、図書館に本を返しに行くたびに新しい本を借りることで、「次は何を読もうかな?」と自然に読書を続けられるようになりました。こうして、読書と図書館通いが生活の一部になったのです。
図書館で簡単な本を借りて、読書生活が始まった
読書を始める際に最も大切なのは、「最初のハードルを下げること」です。いきなり難しい本に挑戦して挫折するよりも、簡単な本から少しずつ慣れていく方が大事です。
まずは図書館に足を運び、自分の興味がある分野の「マンガや図解本」を借りてみましょう。そこから少しずつレベルアップしていけば、読書が楽しくなり、学びの幅も広がります。
- マンガ形式やDVDを最初に読んでみる
- 最初の段階で難しい本は読めない
- 最初はハードルを下げる